こちらで紹介するのは、海外の怖い話好きの一部で話題となった「意味がわかると怖くない話」です。

そのため、途中までは怖そうな雰囲気なのに、読み終えた時には一瞬で恐怖が消滅してしまう怪談もどきばかりを、集めております。
そのため、オチが分かっても怒り出さない温厚な人だけ、先にお進みください…
読書家の少年
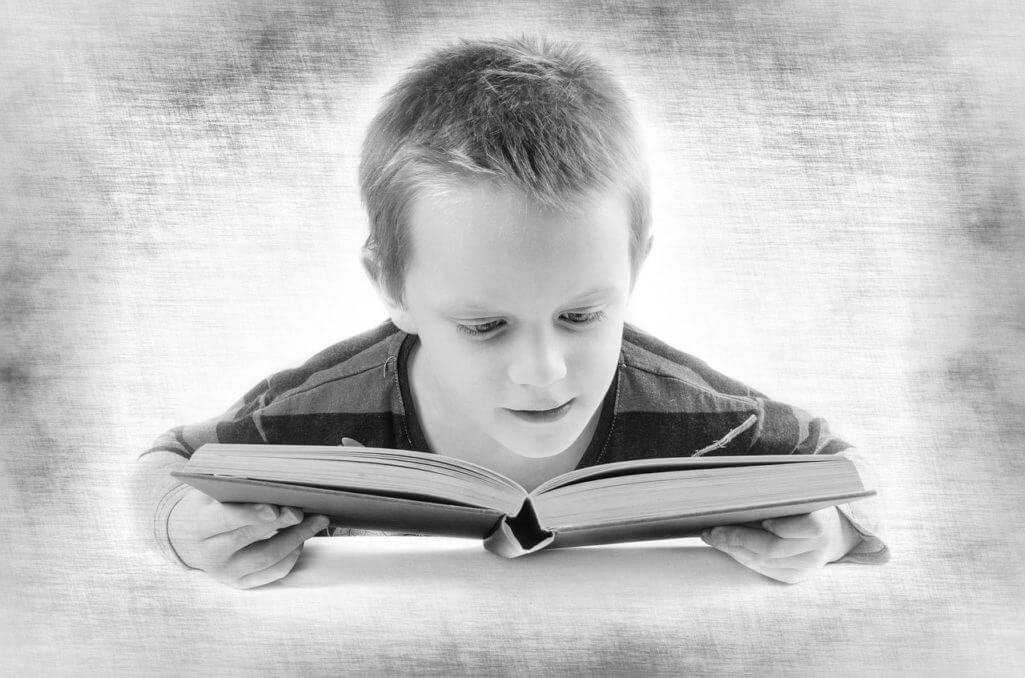
今から数十年前、ある少年の身に起こった悲劇のお話です。
友達とスポーツをするよりもゲームで遊ぶよりも読書が好きだった少年は、近所にある小さな本屋へ行くのが何よりの楽しみでした。
少年は興味のある本を片っ端から購入して、毎日活字の世界に入り浸っていたのです。
しかし田舎の小さな本屋に並ぶ本の数は少なく、やがて少年の興味を引く本が尽きてしまいました。
「すいません、何か面白い本はありませんか?」
少年が店主の老人に尋ねると、レジカウンターの下から一冊の古ぼけた本を取り出しました。
真っ黒な表紙に「DEATH」とだけ書かれた本が、少年は読みたくてたまりませんでした。
「これは、とても面白い本だから100ドルで売ってあげてもいいけど…絶対に1ページ目を読んではいけないよ」
少年は両親にお金を借りて「DEATH」を購入すると、自分の部屋で夢中になってページをめくりました。
徹夜して読み終えた時、目を真っ赤にした少年は、これまでにないほどの充実感に好風していました。
そして、店主から決して見ないよう言われた1ページ目を、どうしても確認したくなったのです。
「100ドルも出して買ったんだから…僕には読む権利がある…」
生唾を飲み込み、意を決して一ページ目をめくった少年は、驚愕して「DEATH」を落としてしまいました。
1ページ目に印刷されていたのは…
「希望価格 4.99ドル」
悪臭

仕事帰りに職場の同僚たちとお酒を飲みに行った女性は、ついつい飲みすぎてしまい、まっすぐに歩けないほど酔っ払っていました。
なんとか自宅アパートに辿り着き、フラフラになりながら階段を登って部屋のドアの鍵を開けようとしたのですが、おかしなことに鍵が空いていたのです。
「急いで出勤したから、締め忘れたのかな…」
酩酊状態で深く考えるのも面倒くさかった彼女は、ドアを開けてベッドへ向かおうとしたのですが、すぐに異変に気が付きました。
彼女の部屋の雰囲気とは全く違うのです。
それどころか、室内には獣のような悪臭が充満しているのです。
そこで彼女は自分の部屋を間違えてしまったことに気付いたのですが、同時に、奥の部屋でブクブクに太った男が、こちらに背を向けてソファーに座り、グチャグチャと音をたてながら何かを食べているのに気付いたんです…
「やばい…早くここから逃げないと」
耐え難い悪臭で嘔吐しそうなのを必死にこらえ、ドアノブを回そうとした時…
「そこにいるのは誰だ!!!!!」
彼女の方を振り向いた男は、獲物を貪る狼のように真っ赤な口元を大きく開け、睨みつけました。
あまりの恐怖に女性は悲鳴を上げながら、男の部屋を飛び出していったのですが…
太った男は全く状況を理解できませんでしたが、再びソファーに座り直し、ビールを一口飲んで、デリバリーピザを頬張りました。
「くそ…どうせ頭のおかしなベジタリアンだろ…」
悪魔の気配

深夜のハイウェイを走っている僕の車の助手席では、一人の美しい女性が寝息を立てている。
彼女とは、つい1時間前に出会ったばかり。
夜遅くにヒッチハイクしている、彼女を見過ごすことが出来なかった。
「君はニュースを見ないのかい?ついこの前もヒッチハイクをしていた女性が殺されたって、盛んに報じられていたじゃないか」
「そうなんですね。でも、その娘は運が悪かっただけじゃないですか?私は大丈夫。あなたのような優しそうな人の車に乗せてもらえたんだからね」
そんな話をしているうちに、気付けば彼女は寝てしまっていた。
ヒッチハイクで州を横断して親戚の家を目指しているそうで、笑顔をみせていたが、とても疲れているようだった。
薄茶色の長い髪は彼女の寝顔を半分隠し、街頭に照らされキラキラと光っている。
何か楽しい夢を見ているのか、時折口元が微笑むのを見ていると…
僕の体の奥底から、悪魔が唸り声を上げたかのような恐ろしい気配を感じた。
途端に息苦しくなり、額に汗が浮かぶ。
長い間、自分でも忘れていた最悪の前兆は、既に僕の体を内側からブチ破らんばかりで、叫び声を上げそうになるほどだ。
きっと、今の悪魔のような顔をした僕を見たら、彼女は恐怖したに違いない。
つい先程出会ったばかりだが、彼女のような未来のある女性に危害を加えるわけにはいかない。
僕は歯を食いしばりながら路肩に車を止める…
しかし遅かった。
次の瞬間、車内へ鈍い音が響き渡った。
やってしまった…
僕は自分をコントロール出来なかった事を悔やんで、涙が零れ落ちそうになった…
ふと視線を感じて助手席の方を見ると、さっきまで笑顔を浮かべながら寝ていた彼女が、僕を睨みつけていた。
「頼む、理由を聞いて聞いてくれないか…」
そう言い終わる前に、彼女は荷物を持って車を出ると、ドアガラス越しに鼻をツマミながら僕に向かって中指を立てた…
本当に怖い話はコチラ…


